曲突徙薪(きょくとつししん)創刊号
気になるアイツ 〜チャットGPT〜
このコーナー「気になるアイツ」では、銀行ビジネス、デジタル技術、信用リスクなど、私が日頃のビジネスで気になったテーマについて、毎月1つご紹介していきます。初回は話題沸騰のAIについてのお話です。
昨年末あたりから、米国のAI開発ベンチャー企業であるOpenAI(オープンAI)社が開発した、対話型AIエンジン「チャットGPT」についての紹介記事やニュースが、国内メディアでも頻繁に取り上げられるようになってきました。昨年11月末のサービス公開以降、驚くほど自然な会話、的確な返答にて、世界中で大きな話題を呼んでいます。
ーーーーー
ChatGPTは、人間のような自然な文章を生成することができる言語処理のモデルです。このモデルは、大量のテキストデータを学習し、それらのデータから新しい文章を生成することができます。開発者は、ChatGPTをAPIとして提供されているので、アプリケーションやサービスに組み込んで使用することができます。 ChatGPTは、自然言語処理タスクの中でも特に文章生成タスクに特に優れています。
ーーーーー
前の段落の説明は、「チャットGPTをわかりやすく説明してください」という質問に対する、チャットGPT自身の回答です。百聞は一見にしかずです。いまは無料で利用できるので、ぜひともこちらのサイトでユーザー登録をして、一度サービスを試してみてください。Googleアカウントによる認証も可能です。サイトの説明はすべて英語ですが、チャットGPTとは日本語での会話が可能です。
なお、私の「日本の地方銀行がこれから生き残るためには何が必要か?」という質問に対して、チャットGPTは次のような答えを返してきました。
ーーーーー
日本の地方銀行がこれから生き残るためには、様々な戦略が必要になると考えられます。以下に一部挙げられるものです。
新しいサービスの開発: 地方銀行は、新しいサービスの開発によって、顧客ニーズに応えることができます。例えば、インターネットバンキングやモバイルバンキング、貸し付けサービスなどがあります。
情報システムの充実 : 地方銀行は、顧客にとって使いやすい情報システムを構築することで、顧客満足度を高めることができます。
人材育成 : 地方銀行は、人材育成に力を入れることで、高いサービスを提供することができます。
地域密着型のサービス : 地方銀行は、地域に密着したサービスを提供することで、地元の顧客にとって魅力的な銀行となることができます。
Fintechとの連携: Fintechが提供するサービスや技術を活用し、地方銀行のサービスを改善することができます。
ただ、以上の戦略は常に成功するわけではなく、銀行によっても適している戦略が異なるため、自社に合った戦略を見つけることが重要です。
ーーーーー
いかがでしょう? もはや、中にいるアナリストがその場で回答を書いているとしか思えないできばえではないでしょうか?
チャットGPTのGPTとは、Generative Pretrained Transformerの略で、あらかじめ読み込んでおいた膨大な量の言語データをもとに、ユーザーの質問に対する回答として適した言語データを並び替えて出力する機械学習モデルのことです。実際には、2021年末までに収集したWeb上の情報を学習用データとして使用しているようです。
サービスを試していただくとよくわかるのですが、チャットGPTは、どんな質問に対しても実に人間的な自然な答えを返してきます。たとえば中学校の数学の問題を与えると、自信満々で誤った解答を出してきたりもしますので、その答えを鵜呑みにすることはできません。そうした点まで含めて人間的と言えます。また、人間にしかできないとかつては考えられていた、詩や小説の創作もチャットGPTにはできるようです。
GPTという技術の背景を考えると、チャットGPTは学習用データに含まれる「過去の知識」の中から、質問に即した情報を並べ替えて出力するAIと言えます。したがって、過去の知識に含まれない情報をゼロから生み出したり、過去の知識の真偽を判断したりするような機能は持ち合わせていません。一方で世の中の文書のほとんどが、過去の知識の並び替えから成り立っているとすれば、そうした既存の知識を整理した作文のような「作業」は、近い将来すべてチャットGPTに置き換わるものと考えられます。銀行業務を例にあげると、稟議書意見のような文書は、真偽(可否)を判断する権限者のために事実を整理した作文ですから、すべてがこの技術に取って代わられても何の不思議もありません。
グーグル検索以来の大発明とも言われるチャットGPTの今後に、大いに注目です。




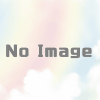
最近のコメント